今回は、中学受験における社会の勉強法について述べてみたいと思います。
中学受験の社会は大学受験の社会の勉強に直結するほど難易度が高かったりします。
大学受験を控えている人は中学受験の社会の勉強がどのようなものかを知っておくのは有益だろうと考え今回記事にしました。
大学受験の社会の勉強法については「新共通テストとセンター試験との違いとその対策(世界史中心に)」で記載してますのでまだの人は読んでみてください。

学力社会と騒がれている現在では中学生から受験するいわゆる中学受験が増えています。
そうした中で、中学受験における社会をどのように勉強すればいいのか悩んでいる人も少なくないのではないでしょうか。
今回は中学受験での社会を勉強すればよいのか、その勉強法を紹介していきたいと思います。また、社会が苦手なお子さんの特徴とどのような勉強をしていけばいいのか記載していきます。
また、おすすめの塾及び参考書を記載しましたのでこちらも併せて読んでみてください。
中学受験の社会(地理・歴史・公民)で必要なマインド

中学受験で社会を勉強していく上で必要な考え方があります。
まず、受験で社会を勉強するにあたって肝に銘じてほしい考えを述べます。
社会は暗記教科ではない
中学受験の社会では、歴史の事件や人物名、地理では各地の地名や特産品、公民での国の様々な制度など、覚えることがたくさんあり、年号や単語だけを単語帳や語呂合わせなどで暗記している生徒をたまにみかけます。
しかし、社会を単語や年号だけの単純暗記と考えるのは今すぐやめましょう。
社会は、全ての事象につながりのある教科で、決して暗記教科ではありません。
歴史上の出来事、身の回りの制度や時事の原因を理解して「なぜこの事象が起きたのか」を考えたり、身近なものと結びつけて体験することが何よりも重要なのです。
そのために、社会の学習は自分が今生きている社会とのつながりを意識するきっかけだと考えましょう。
中学入試社会の出題傾向
また、近年中学入試では、教科に関わらず思考力が問われる問題が出る傾向にあり、社会も自分の意見や考察を記述する問題が増えてきています。
例えば2019年の入試では、ある学校で「2020年に導入が検討されていたサマータイムについて、メリットを考えなさい」という問題が出題され、また別の学校では「デメリットを考えなさい」という出題されました。
当然ながらこのような問題は、単語を丸暗記しているだけでは太刀打ちすることができません。しっかりとその事象の原因や本質を理解し、使える知識として理解を深めておかなくてはいけないのです。
中学受験の社会の問題構成は意識しよう
学校によっても傾向は異なるのですが、中学受験での問題構成は「時事問題、公民、地理、歴史」となっていることが多いです。
6年生に習う公民が一番最初に来て、萎えてしまう小学生も多いです。
もちろん受験校によってその問題構成や、年度による傾向は変わってくるので絶対ではないので、ご自身が受験する学校の過去問を読み対策してください。
では、この社会についてどのような勉強がおすすめか記載していきます。
中学受験の社会(歴史・地理・公民)のおすすめ勉強法
 中学受験の社会を勉強するのにあたりどのような勉強をしていけばいいのか、塾講師の観点から解説していきます。
中学受験の社会を勉強するのにあたりどのような勉強をしていけばいいのか、塾講師の観点から解説していきます。
今回の記事では、これらの問題の勉強法をそれぞれ解説していきます。
時事問題の勉強法とは?

前提として、時事問題に対応するためには、世の中の出来事に対し、多くの知識を持っていなければなりません。
例えばですが、「日韓問題」に関するニュースを見たとしましょう。仮に知識のないうちにニュースを見ただけでは、日韓問題を理解し、“その場で記憶する”というのは困難です。
このことからも、時事問題に公民、地理、歴史という知識は必要であるとわかります。
あとはとにかく、常日頃からニュースや新聞を毎日チェックする必要があります。1日10分、20分でもニュースに目を通すと、「あれ?これ昨日もやってた内容だな」と気づくはずです。
よく見る、ということは社会的に重要な内容であり、時事問題として問われやすいため、そう思ったニュースは要チェックです。最近では憲法改正に関する議論や韓国との貿易交渉などが重要なニュースと言えます。
時事問題では、時として「作文問題」なども出題されることがあります。
そのため、毎日ニュースなどを見るだけでなく、見たうえで、その内容に関して、自身の考えを持ち、その上で他者の考えも取り入れる必要があります。
自分と違う考えを否定するのではなく、なぜ、そのような考えになるのか、と思案することでより知識を得ることができます。
さらには本番になったとき、「自分の考え以外にもこうした考えもある」と、自身が広い視野を持っているとアピールすることができます。
公民の勉強法とは?

中学受験での公民はあまり複雑なものがでることはありません。むしろ暗記などがメインとなってきます。
公民でも、ニュースや新聞を見るということは非常に生きてきます。ニュースなどを見ていれば、必然と国会や内閣などの単語が目に入ります。そうしたときに、わからなかった単語はメモをしておくとよいです。
その上で、内閣はどんな仕事をするのか、国会とは何が違うのかなどを本質的に理解しながらニュースを見ていけば、自分の中で知識を体系化させながら暗記することができます。
この勉強法は、公民の対策と同時に時事問題の対策にもなるのでオススメです。
地理の勉強法とは?

地理という科目はさまざまな分野に分かれます。その中でも最重要な位置付けなのが、“気候”の分野です。最優先で気候を覚え、その後に地形などを覚えていくと良いでしょう。
というのも、地理では農業やその国の風土について問われることが多く、そもそも気候について理解し、覚えていないとそういった問題に対応することができません。
特に、日本全国の雨温図を押さえる必要があります。日本一降水量の多い三重県尾鷲市の雨温図から瀬戸内海側、日本海側、北海道とこの4箇所をざらっと押さえた上で細分化して覚えていく必要があります。
隣り合っている立地なのに、微妙に違う気候の場所は問われやすいので注意しておきましょう。
気候の次に問われやすいのは資源に関する問題です。どこでどのような資源が取れるのかなど、第10位などを語呂合わせで覚えておきましょう。語呂合わせと理解のセットをオススメします。
歴史の勉強法とは?

まず、教科書の太字の単語はしっかりと暗記しましょう。ただし、単純な暗記だけでは対応できない問題もあります。例えば、征夷の夷とはどういった意味か、といった問題です。
こういった問題に対応するために、単語だけを覚えるのではなく、単語の成り立ちや、その単語が持つ歴史的背景もしっかりと把握しておかなければなりません。とはいえ、ただ暗記するだけではかなり苦しいと思います。
そこで、空き時間などで「日本の歴史」などの漫画を読むなどすると、それだけで対策になるのでオススメです。
社会が苦手な子の特徴と対処法

「勉強がわかったとしても、なかなか社会ができるようにならない」
そんなことを考えられておられる方もおられるでしょう。
そこで、社会を苦手とする生徒の特徴とその対処法について述べていきます。
テストのためだけに丸暗記して勉強してきた
社会をひたすら暗記科目と考えていてなかなか点数があがらず嫌いになる生徒がいます。
中学受験での社会は身の回りのことに興味関心を惹きつける問題が出題されます。
知識は必要ですが、難関中学は知識のみで乗り切れるほど単純ではありません。点数が取れなくてさらに嫌いになる傾向にあります。
そこで、対策として子供に身の回りの社会問題でなぜそのような背景があるのかについて興味関心を抱かせる必要があります。
例えば公民で裁判所がイメージつかなければ近くの地方裁判所に見学にいくとか、社会の知識が実は身近なことなのだと意識させるようにしてあげましょう。
社会の勉強を後回しにしてしまった
中学受験で算数と国語がウェイトを占めどうしても社会は後回しになる傾向にあります。
しかも、社会は、短時間で仕上げることができるとついつい後回しになったりします。
社会は上述の如く身の回りのことの興味関心につなげることができる科目です。
そこで、後回しにするのではなくなるべく早い段階から社会に興味を持たせて点数を取らせるようにするとよいでしょう。
覚えることが嫌い
社会は、思考力が問われることとはいえ、ある程度暗記ができなければ勝負になりません。そこで暗記をそもそもせずに社会を嫌う生徒もいます。
しかし、中学受験に暗記はある程度必要になってきます。
全く暗記に頼らずに戦うことはできません。そこで、暗記が嫌いとはいえ、暗記しなければなりません。
そこで、知識を細切れにして覚えることを少なくしつつ繰り返し暗記していくようにしましょう。
暗記が嫌いでも、覚えらるようになれば徐々に暗記が得意と考えて好きになります。
間違った方法で勉強している
中学受験社会のおすすめの塾は?
 ちなみに中学受験をする小学生が中学受験の社会のおすすめの勉強法ですが都内なら、中学受験専門個別指導塾の中学受験ドクターがおすすめです。
ちなみに中学受験をする小学生が中学受験の社会のおすすめの勉強法ですが都内なら、中学受験専門個別指導塾の中学受験ドクターがおすすめです。
もし、中学受験を考えておられるなら中学受験は大学受験と似て非なるもので独学で勉強をすることはほぼほぼ無理です。
一部の例外が塾に行かずに御三家に入ったなどと話もありますが基本奇跡に近いです。
理由としては、教師の質が圧倒的に高いからです。
以前私は、中学受験専門個別指導塾の中学受験ドクターの面接を受けに行ったことがあります。
その面接内容は、国語と数学の二教科のうち選択する方式だったのですが、私は国語を選びました。国語では長文問題と漢字問題が出題されたのですが、その内容が某有名中学の国語問題を改変したものだったのですね。
私はたまたまそのテストを分析していたのでギリギリ合格点を取れたのですが(長文問題をそこそこ落としたらしいが漢字は満点だったそうな…)ここで働いている教師はかなり質が高いというのを実感しました。
なぜなら御三家の入試レベルを取れる人しか採用されない訳ですから。厳選された教員が徹底的に教えるとそりゃ成績伸びる訳です。
また、集団塾としてはSAPIXがいいでしょう。SAPIXについては「中学受験 SAPIXの授業 (学研新書)」が詳しく中学受験の授業について書かれており、普通の子が中学受験で勝ち抜くのはいかに大変かがわかります。
中受は塾が必要ですが、大学受験は独学でも意外といけちゃうところが大きな違いかもしれませんね。今回はお疲れ様でした。
高校受験の社会については「高校受験の社会の対策・平成30年度都立高校受験の問題分析」に詳しく記載してあります。




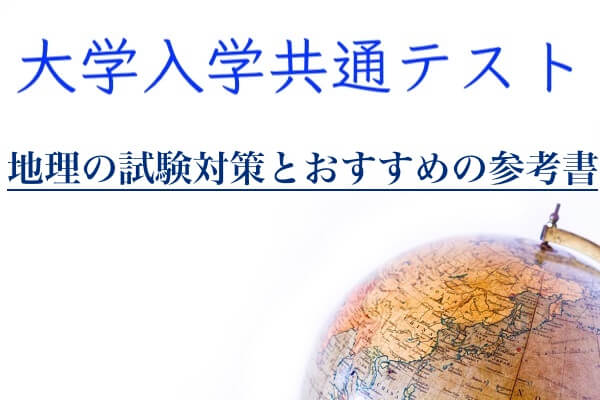
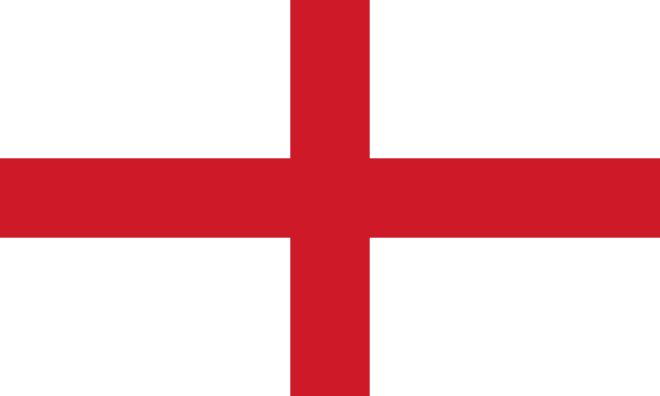
コメント